わが家には、昭和18年生まれの爺さんのほかに、昭和26年生まれのおじさん、精神障害者で通院中。もう一人は、昭和28年生まれで透析治療中の身体障害者のおじさんです。1番年下のおじさんは、車椅子生活で旦那の伯父にあたります。真ん中のおじさんも旦那の伯父。
年齢順に亡くなるとしたら・・
年齢順に亡くなるとしたら爺さん→おじさん→おじさん(車椅子)となります。

でも車椅子のおじさんは透析治療をしているから寿命は、普通の人より短いのかも。
旦那は、介護に関して一切手伝っていないんですよ。夜勤もあるし、そこは私も求めてはいないのですけど、婆さん(義母)は亡くなってしまったし車の運転はできないし、爺さんも足腰がヨボヨボなので今は私一人でやっているような状況です。
目次
おじさんが亡くなった場合、相続はどうなるの?
家族が高齢だと介護は、避けて通れない問題です。ただ、おじさんが亡くなったとき相続どうなるの??と心配になったので金融機関で聞いてみました。結論から書くと・・

おじさんたちの相続は旦那にも私にも相続の権利はありませんでした。
死んだらお金がかかる!
わが家では、タダでは死ねないが合言葉。2019年より以前は通帳にお金が入っていても、死亡届を出すと即座に口座が凍結され葬儀費用すらおろせませんでした。
「死にそうになったらお金を先におろしてくれば良いよね・・」でも出来ないものです。2019年、40年ぶりに相続法が見直され150万円を上限に使い道を問われることなくお金が引き出せるようになりました。
葬儀費用は平均120万円
葬儀にかかる岐阜県の費用の平均は120万円程です。おじさん二人は家族葬にする予定なので、もう少し安くおさまるかもしれませんが、葬式はお金がかかります。
相続の手続きは相続人の数が多いと遺産分割の手続に手間と時間がかかります。葬儀費用の支払いが滞るのも避けたいと思っていたので法改正は大歓迎です。
伯父さん伯母さんの両親に相続権
同居の家族に伯父(叔父)、伯母(叔母)に子どもや配偶者が居ない場合・・(うちのケース)、その兄弟姉妹に相続の権利があります。おじさんの兄弟姉妹全員に相続の権利があるのです。
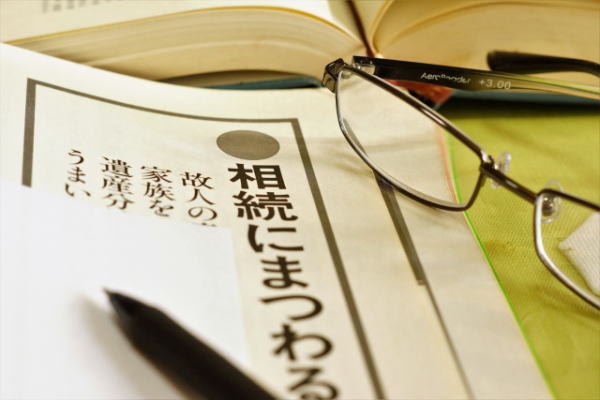
伯父さん伯母さんの両親が生きていれば、両親に相続権があります。
配偶者がいれば配偶者に相続権があります。子どもがいれば子どもに相続権があります。
伯父さん(叔父さん)伯母さん(叔母さん)に子どもが居ない場合、兄弟姉妹に相続権があるんですね。

甥や姪には、相続する権利はありません。もちろん甥の妻である私にも!!
おじさんおばさんの相続順位
伯父(叔父)さん、伯母(叔母)さんに配偶者がいれば第1順位の配偶者が相続します。子どもがいれば第2順位の子どもが相続します。配偶者と子どもがいれば、配偶者と子どもに相続の権利があります。おじさんの配偶者は、離婚しているので権利がありません。離婚して相手が親権を持った子どもには、相続の権利が発生します。
子どもがいない場合、第3順位の本人の親に相続の権利があります。本人の父親は20年前に亡くなり母親も亡くなっています。第1順位 第2順位 第3順位が居ない場合、第4順位の兄弟姉妹が相続することになります。
相続の順位
- 第1順位 配偶者
- 第2順位 子ども・・子どもはいない
- 第3順位 直系尊属(伯父さんの両親)・・父親、母親ともに死亡
- 第4順位 兄弟姉妹・・7人の兄弟姉妹のうち2人は死亡→それぞれの子どもの数(3人+2人)
法律上 第4順位の兄弟姉妹は既に2人亡くなっています。この場合、その子どもたちに相続権が行きます。その子ども全員の住所も分からないし面識もありませんが、通帳に150万円以上の残高があったら相続権がある人全員に対して手続きが必要なのです。

全員分を揃えるのに時間がかり労力も大変です。手続きは以下の通りです。
- 実印登録を取り寄せてもらう(手続きをするためのお礼も必要)
- 書類に著名捺印してもらう。
介護しても養子縁組をしないと権利は無い
つまり、たとえ介護を一生懸命にしても甥も姪も養子縁組でもしない限り相続する権利は無いんですね。ただ、家族というだけで、おじさん二人の生活にかかる費用、病院の入院費、病院に行くまでの交通費などが発生しました。
当時は精神障害者の認定を受けていなかったですし、別々に暮らしていたので、アパート代も電気代も水道代もガス代も全部我が家で支払っていました。精神病院の入院費は、とても負担だったし、生活費も二重にかかっていたため経済的にも精神的にもきつかったです。
おじさんの兄弟姉妹、その子たちである甥、姪にあたる人からも一度も支援してもらっていません。
同居する親族だけが相続人ではない
同居する親族が相続人だと思ったら違うんですね。同居していたとしても、甥っ子にも姪っ子にも、相続の権利は無いのです。

長男の家で見るしか無いんだねェ損な役回りだね・・長男の嫁は・・
私は楽天家なので、ノンキに損だよな・・長男っていうだけで負担が多い・・と考えていました。費用の負担をしていたのは、爺さんで爺さんも兄弟だから仕方ないみたいなところがあったので。
方法①遺言書を書いてもらう
甥や姪に相続権は無いので、生前遺言書を書いてもらえば遺言書が有効となります。しかしうちのオジサンは、統合失調症なので遺言書を書いてもらっても有効性が認められない可能性が高いんですね。
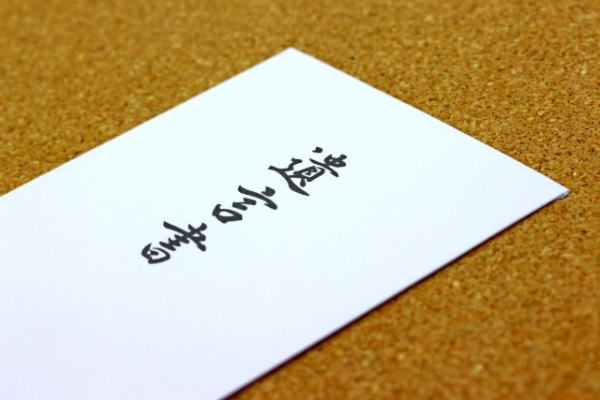
統合失調症だけでなく認知症、高齢などを理由に遺言者が無効となることがあります。
方法②兄弟姉妹に対して遺産の相続放棄をお願いする
おじさんが亡くなった場合、兄弟姉妹が相続人となるので、遺産の相続放棄をお願いすると良いのかもしれません。

故人が負債を多く抱えていた場合、逆に相続を辞退されることもあります。
プラスの財産(資産)とマイナスの財産(借金)
故人にプラスの財産(資産)とマイナスの財産(借金)がありマイナス(負債)が多い場合、借金(負債)も引き継ぐよりは遺産相続を辞退されることもあります。
遺産相続放棄の手続きは司法書士、行政書士、弁護士などに依頼します。ただ相続人の数が多くなれば多くなるほど揉めやすく複雑になります。人数に応じてお金もかかるし手続きが面倒なので依頼する人が多いみたい。
相続放棄の期限は、3ヶ月以内で一度行うと取り消すことはできません。亡くなってから慌てることがないように考えておかなければ・・。
生命保険の受取人を変更しておく
統合失調症のおじさん本人が入った生命保険の受取人も変更しました。亡くなった場合の受取人を本人から爺さんに変更していたのですが、爺さんも高齢のため家族で話し合い旦那に変更しました。
長いあいだ保険金を掛けていたことと掛け金の支払いが終了しているせいか生命保険の担当者のかたに来てもらい、本人に承諾してもらいながら簡単に変更できました。

生前、意思確認ができるうちに手続きしておいて良かった~~
透析患者の寿命
50才の透析患者の平均寿命は男性14.6年、女性16.7年。60才の透析患者の平均寿命は男性9.9年、女性11.3年です。透析を始めたのは65才頃からだったので・・75才ぐらい・・。81才(平均的な男性の寿命)と比べると数年は短いようです。

同居している叔父さん(伯父さん)、叔母さん(伯母さん)の相続は、同居する親族が引き継ぐものだと思ってた
嫁の介護義務問題
同居しているので引き続き雑務はこなしていきますよ♪でも本当は扶養の義務は兄弟姉妹にも均等にあるので、こんなこと言う立場ではないし言われる立場でもなかったんですね・・

嫁がもっとちゃんと介護(面倒を見る)をすれば良いのに
うちなんか、義母とセットで?文句言われまくっていましたからね。内情知らない人に散々な言われ方をして傷ついたものですよ。

はああ??嫁の私には介護する義務無いんですよ
言える立場でも言えないものですよね。そんなこと。田舎の嫁ですから。
介護をしても面倒を見ても嫁なんて損な役回りなのかもしれません。
嫁も特別寄与料の請求ができる
同居してるだけで本当は面倒を見る義務はありません。でも現状、嫁である私が介護の中心になったほうが良いに決まっているので、やっているかんじです。嫁というだけで重い荷を背負わなければいけないのに相続権は無いっていうね・・(お金欲しくてやってるわけではないですけど)

介護していた長男の妻に「特別寄与料」の制度ができました
嫁にとっては朗報ですが条件は以下の通りです。
- 被相続人に対して無償で療養看護をしたこと
- そのことによって被相続人の財産が維持、増加したこと
- 被相続人の親族であること
義父母の介護をしてきた嫁には、本来相続する権利はありませんが、遺産請求は可能です。
特別寄与料の請求ができますが介護や貢献していた証明が必要です。過去の記録や日記帳などは保存しておくと良いようです。
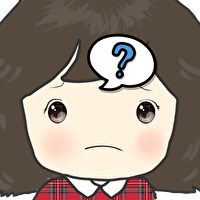
私の場合、長男の嫁ではなくて甥っ子の嫁なんだけど、どうなるんだ?複雑。
6親等以内の血族
6親等以内の血族、孫、ひ孫、甥、姪やその子ども、従姉妹、曾祖父母、大叔父、大叔母なども介護していた場合特別寄与料が認められます。特別寄与料の請求方法に特別な手続きが不要で話し合いで合意すれば支払われます。
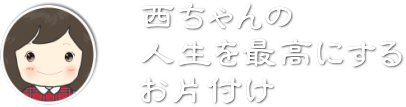





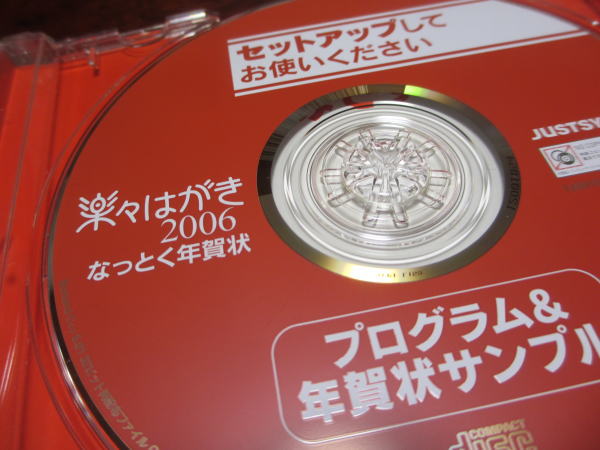




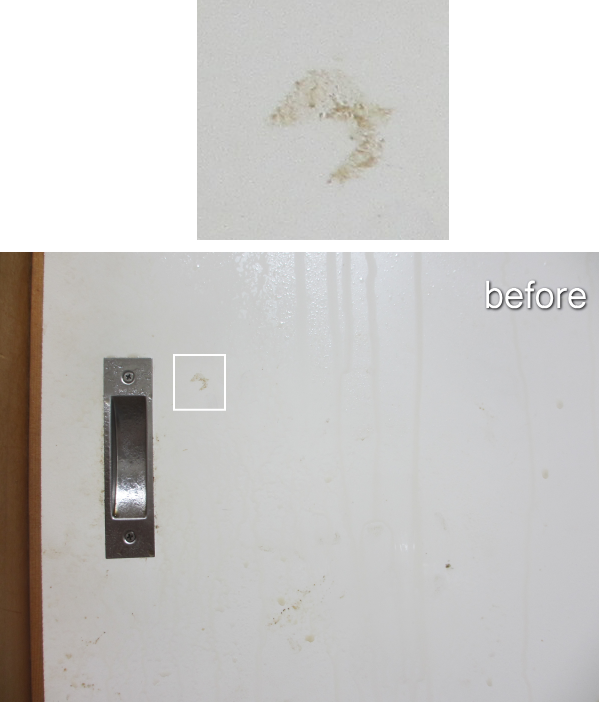
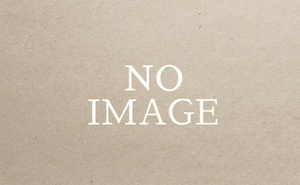
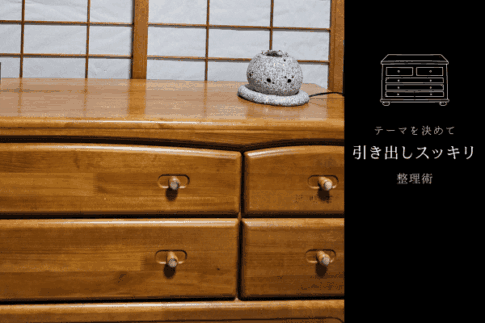



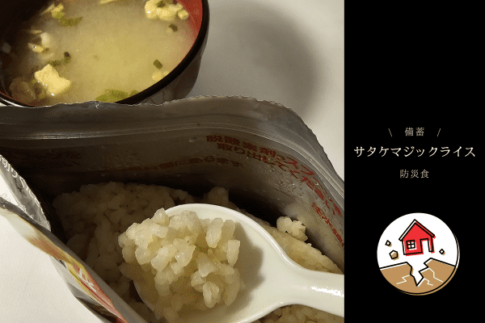
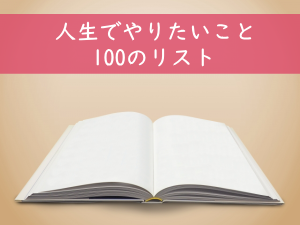
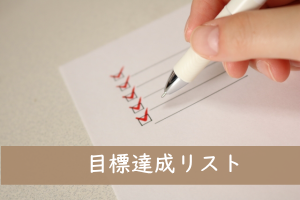


西ちゃんさん こんにちは!
凄い!よく調べましたねぇとても分かりやすいです。
でも、法律ってややこしいですねぇ
面倒をみた人が相続の権利がないなんて、ありえない!
お金をもらうために面倒を見るわけではないけれど、
何もしていないひとに相続の権利があって、面倒をみた人は
ないのは不思議です。
でも、西ちゃんさんは偉いですね。
2人のおじさんの面倒を見て!
きっと色々なことがあったと思います。
でも、おじさんたちもきっと感謝しているはず!
私はまだまだ甘ちゃんです。
obasann51さん、いつもコメントありがとうございます。いや~~~~今まで一緒に暮らしていて、ゆくゆくは、おじさんの遺した遺産を普通に家族である自分たちが相続できるものと思い込んでおりました。
遺産目当てで介護とかしているわけではないのですが・・ムムムっと思いました。
何だか腑に落ちないものですね。
遺産というほど、お金は残していないのですが、、、いずれにしても兄弟姉妹に印鑑証明をもらったりしなければいけないようです。
看取り看護をしている友人の話によると、「死ぬか死なないか?の状態になると慌てて家族がお金をおろしに行くよ!」と言っていました。
大きい爺さんが死んだとき、兄弟姉妹(7人)とその子どもたち(6人?)に印鑑証明をもらうのに難儀しました。
大きい婆さんが死んだときは、通帳の残高をオジサン名義の口座にしたら耳が遠い人だったので泥棒呼ばわり?されました。笑。
少ない金額でも通帳に入っていたので手続きにお金がかかりました。
今年死んだ婆さんは、あらかじめ余命宣告されていたため生きているうちに通帳の取引をしない手続きをしました。死にそうになったらお金をおろしにいこうと思っていましたが、死んだ日が土曜日だったのでお金をおろしにいけませんでした。(カードを作っておくべきだったと反省)
そして今に至る・・というかんじです。
何事も面倒なことを経験したため学習だけはしていますけど、毎回バタバタですね。
次に葬儀があったら、死亡診断書をもらう前にお金をおろしておくことを肝に命じている私です。
西ちゃんさん 勉強になります。
私にも年老いた両親に旦那の母親がいます。
いつどうなるか分かりません。
「死ぬか死なないかのときにお金をおろしにいく」私も、聞いたことがあります。
お金をおろしにいったり葬儀の手続きで、本当の悲しみは後からやってくると
聞きました。
西ちゃんさんを参考に、もし両親たちがそうなったときは死亡診断書をもらう前におろしにいきますw
obasann51さん、「死んでる!」と誰かが発見したら、葬儀屋に電話をかけてる横で散らかっている場所を片付けたりwしかも慌てている割には片付けが進まないという・・体が1つしかないので大変なんですよね。
看取りをしてもらったら死亡診断書をもらう前に「お金」超重要!!笑。実際には市役所などの届けを出す前ならおろせるのかもしれないですけど。葬式なんて「慣れる」ものではないですけど毎回嵐みたいです。田舎だから仕方ないですけどね。